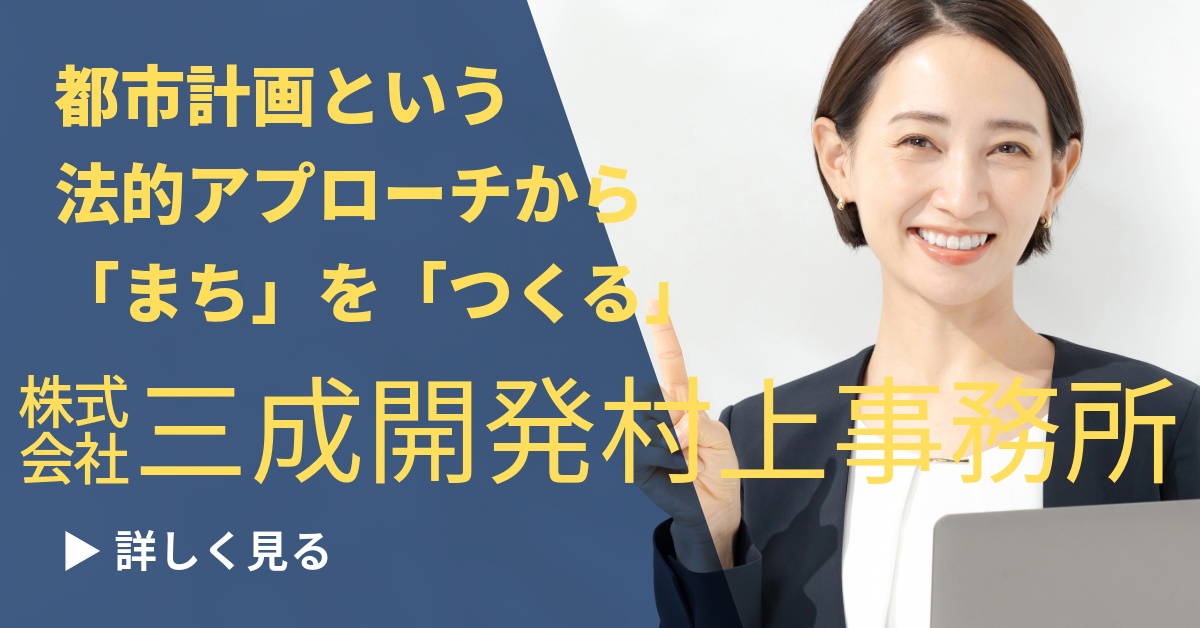熊本の経営事項審査

経営事項審査
CCUSの運用が「経審の点数」に直結する時代へ:登録だけでは加点されない本当の条件とは?
公共工事を受注する建設会社様にとって、経営事項審査(経審)の評点アップは、企業の存続と成長を左右する最重要課題です。そして、近年この経審の評価において、建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用が決定的な要素となってきています。
「CCUSの登録は済ませたけれど、本当に経審で加点されるのか?」「現場での打刻運用が難しくて、協力会社にどう説明すればいいのか?」といった疑問を抱え、システムを十分に活用できていない会社様も少なくありません。
CCUSは単なる入退場管理システムではなく、国が建設業界の未来のために推進する重要な仕組みです。その導入と活用は、経審の評点を高めて入札競争力を上げるだけでなく、技能者の処遇改善や人材確保にも直結します。
本記事では、建設業専門の行政書士が、CCUSの基本から、経審で確実に加点を取るための具体的な運用戦略、そして導入の際に陥りやすい落とし穴までを、誰にでも分かりやすく徹底解説します。この記事を読み終えることで、貴社がCCUSを真に経営に活かし、安定した公共工事の受注に繋げるための道筋が明確になります。
建設業を経営する上で、経営事項審査(経審)の評点確保は、公共工事を受注するために非常に重要です。特に社会性等(W点)の対策として「法定外労働補償制度」への加入を検討されている方も多いのではないでしょうか。
しかし、「国の労災保険(法定補償)と何が違うのか」「どの保険でも加入すればW点は加点されるのか」といった点を、明確に説明するのは難しいかもしれません。もし、その理解が曖昧なまま制度を選んでしまうと、保険料を支払っているのに経審の加点対象にならなかったり、万が一の事故の際に会社の経営を揺るがす高額な賠償責任に対応できなかったりする恐れがあります。
この記事では、法定外労働補償制度の基本的な役割から、経審で加点を得るために必要な厳格な条件、そして建設業の経営者としてリスクに備えるための制度の選び方まで、専門家の視点でやさしく解説します。評点アップと会社のリスク管理を両立させるための、正しい知識を身につけてください。
経営事項審査「建設機械の保有状況(W5)」徹底解説。点数計算とリース・書類の注意点
経営事項審査(経審)の「建設機械の保有状況(W5)」について、点数の計算方法や対象となる機械の種類、リース契約の扱いで悩んでいませんか。
W5は、会社の技術力を示す重要な評点ですが、その審査は非常に厳格です。例えば、必要な検査記録(特定自主検査済証など)やリース契約書の不備が一つあるだけで、保有している機械が「0台」として扱われ、点数が全くもらえない事態も起こり得ます。
さらに、W5の点数を上げようと機械を導入した結果、財務評点(Y)が悪化し、かえって総合評定値(P点)が下がってしまうケースも少なくありません。
この記事では、W5の基本的な仕組みから点数計算の方法、審査で必要な書類の準備、そして財務バランスまで考慮した評点アップの戦略まで、建設業専門の行政書士が分かりやすく解説します。
経営事項審査(経審)のCPDとは?W点の加点と評点アップの仕組み、申請の落とし穴を解説
建設業の経営事項審査(経審)において、技術者の能力向上への取り組みが「W点」として評価されることをご存知でしょうか。これがCPD(継続的専門能力開発)による加点です。しかし、CPDは「ただ単位を取得すれば点数がもらえる」という単純なものではありません。計算方法や申請には独自のルールがあり、それを知らないと努力が評価に結びつかない危険性もあります。
この記事では、CPDの基本的な意味から、経審のW点でどのように評点に加算されるのか、その具体的な仕組み、そして申請時に陥りやすい「落とし穴」までを、経審の専門家が分かりやすく解説します。評点アップに繋げる戦略的な活用法を学びましょう。
経営状況(Y点)とは?経審の評点を決める8つの指標と改善策を専門家が解説
公共工事の受注を目指す上で避けては通れない経営事項審査、通称「経審」。その評価項目の中に「経営状況(Y点)」というものがあります。このY点が低いと、公共工事の受注が著しく不利になることをご存知でしょうか。Y点は会社の財務的な健全性を示す、いわば「経営の通知表」です。しかし、その評価の仕組みは複雑で、「どうすれば点数が上がるのか分からない」とお悩みの経営者様も少なくありません。この記事では、Y点の基本から、評点の根拠となる8つの指標、そして評点を上げるための具体的な経営改善策まで、建設業専門の行政書士が小学生にも分かるように丁寧に解説します。会社の未来を切り拓くため、まずは自社の経営状態を正しく知ることから始めましょう。
経審の電子申請はGビズID取得から!JCIPとの連携手順と注意点
令和5年1月から、経営事項審査(経審)の申請は、原則として電子申請で行うことになりました。「何から始めればいいのか分からない」「GビズIDやJCIPといった言葉の意味が掴めない」。そんなお悩みを抱える建設会社の経営者様やご担当者様も多いのではないでしょうか。この記事では、数々の建設会社様をサポートしてきた行政書士が、電子申請の第一歩であるGビズIDの役割から、建設業専用システムJCIPとの関係、そして両者を連携させる具体的な手順まで、一つひとつ丁寧に解説します。便利さの裏に潜む評価点ダウンのリスクを避け、会社の価値を正しく守るための知識が身につきます。新しい時代の経審へ、確実に対応していくための第一歩を踏み出しましょう。
熊本県の建設業向け|ユースエール認定で経審10点アップ!申請手順と注意点を専門家が解説
熊本県で建設業を営む経営者様、ご担当者様へ。
「経営事項審査の評点を少しでも上げ、公共工事の受注機会を増やしたい」「将来を担う、意欲のある若手人材を確保したい」これらは多くの会社が抱える共通の悩みではないでしょうか。
実は、この2つの重要な課題に同時にアプローチできる有効な手段として、国が若者の採用や育成に積極的な中小企業を後押しする「ユースエール認定制度」があります。
この認定を受けることで、経営事項審査(経審)の社会性等(W点)で10点の加点が得られるだけでなく、会社のイメージが向上し、若手人材の採用競争において大きなアドバンテージとなります。
この記事では、ユースエール認定制度の基本から、熊本労働局への具体的な申請手順、準備すべき書類、そして認定を受けた後の経審での加点手続きに至るまで、専門家の視点から網羅的に解説します。会社の成長に繋がる次の一手として、ぜひご一読ください。
【熊本県版】くるみん認定で経審のW点を10点加算!申請手続きからP点最大化戦略までを完全解説
熊本県内で公共工事への入札参加を目指す建設業者の皆様、「経営事項審査(経審)の総合評定値(P点)を、あと少しでも上げたい」とお考えではないでしょうか。しかし、完成工事高(X1評点)や技術職員数(Z評点)をすぐに伸ばすのは、簡単なことではありません。
実は、日々の売上や人員確保とは別の視点から、会社の評価を着実に高める方法があります。その中でも特に有効な戦略の一つが、厚生労働省が定める「くるみん認定」の取得です。
「子育てサポート企業」の証であるこの認定は、経審において社会性等(W点)が一律で10点加算され、最終的なP点を1.5点も引き上げる効果が見込めます。本記事では、熊本労働局への具体的な申請手続きから、専門家選びの重要な注意点、そして取得した認定をいかにしてP点の最大化に繋げるかという戦略まで、経審の専門家が網羅的に解説します。
えるぼし認定で経営事項審査の評点を上げる方法とその手続きについて
公共工事の受注競争が激しくなる中、経営事項審査(経審)の評点を少しでも高めることは、すべての建設業者様にとって重要な経営課題です。近年、その評点を10点加算できる新しい制度として「えるぼし認定」が大きな注目を集めていますが、「言葉は聞いたことがあるが、詳しくは知らない」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「えるぼし認定」がどのような制度で、なぜ経審の評点アップに繋がるのかという基本から解説します。さらに、認定の段階や評価基準、加点を受けるための具体的な申請手続き、そして認定取得までの全体の流れまで、専門家の視点から順を追ってわかりやすく説明します。
女性が活躍できる職場環境づくりへの取り組みが、企業の競争力に直結する時代です。この制度を正しく理解し活用することが、貴社の企業価値と経審の評点を同時に高めるための鍵となります。
経営事項審査のCCUS対応で評点アップ!導入手順から運用の注意点まで
経営事項審査の書類に新しく加わった「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置」という項目を見て、一体何をすれば評価されるのか、お悩みではありませんか。また、CCUS(建設キャリアアップシステム)という言葉は聞くものの、経審の評点とどう関係するのか、具体的に何から手をつければ良いのか、分かりにくいと感じている方も多いでしょう。
この記事では、建設業専門の行政書士が、この新しい評価項目の正体であるCCUSについて、その基本から経営事項審査で評点を着実にアップさせるための具体的な方法、そして導入後の注意点まで、6つの章にわたって体系的に解説します。
最後までお読みいただければ、CCUS対応への漠然とした不安が解消され、会社の評価を高めるための明確な次の一歩が見えてきます。
【令和7年改正】経営事項審査の新しい評価「資本性借入金」とは?仕組みから申請方法まで
公共工事の受注に不可欠な経営事項審査。会社の経営状態を評価する上で、特に財務の健全性は評点を大きく左右する重要な要素です。「自己資本をすぐに増やすのは難しい」「借入金が多くて評点が伸び悩んでいる」といったお悩みをお持ちの建設業者様も多いのではないでしょうか。
実は、そのお悩みを解決する新しい選択肢が登場します。それが、審査基準日が令和7年3月31日以降の決算から適用される「資本性借入金」の制度です。この制度は、特定の条件を満たした借入金を、経審の評価上は負債ではなく「自己資本」として加算して評価するという画期的な内容です。うまく活用すれば、財務評価を大きく改善し、総合評定値の向上に繋がる可能性があります。
しかし、どのような借入金でも対象になるわけではなく、「返済期間が5年を超える」「万が一の際の返済順位が低い(劣後性)」といった専門的な条件をクリアし、さらに公認会計士などの専門家による証明を受けた上で、定められた手順に沿って申請しなくてはなりません。
本記事では、この新しい「資本性借入金」の制度について、建設業の経営事項審査を専門とする行政書士が、その基本から評点アップの仕組み、対象となるための具体的な条件、申請手続きの流れ、そして活用前の注意点まで、誰にでも分かるように順を追って詳しく解説します。
建設業の「現場専任」とは?わかりやすく解説【経営事項審査の評価も】
公共工事の受注や、大規模な民間工事をおこなう際、「現場に専任の技術者を配置してください」と言われ、戸惑った経験はありませんか?
「現場専任」という言葉は聞いたことがあるものの、具体的にどのような工事で必要なのか、また、他の現場と兼任してはいけない理由は何なのか、疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、建設業法に基づいた「技術者の現場専任」のルールから、経営事項審査での評価、違反した場合のリスクまで、専門家がわかりやすく解説します。この記事を読んで、現場専任の制度を正しく理解し、適正な施工体制を築くためのヒントにしていただけますと幸いです。
建設工事において、元請業者が作成を義務付けられている「施工体制台帳」は、工事の安全と品質を確保し、下請構造を透明化するための重要な書類です。しかし、「作成義務があるのはどんな時?」「何を書けばいいの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、元請業者の皆さまが知っておくべき施工体制台帳の基本から、作成方法、記載すべき内容、そして作成を怠った場合の罰則まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、施工体制台帳に関する不安を解消し、適正な建設工事の管理にお役立ていただけます。
【2025年経審改正】資本性借入金の活用法を徹底解説。評点アップの仕組みと注意点
公共工事の入札に参加する建設業者の皆様にとって、経営事項審査(経審)の評点は事業の未来を左右する重要な指標です。その経審のルールが2025年から大きく変わり、新しい評価制度が導入されることをご存知でしょうか。
今回の改正で最大の注目点が「資本性借入金」の活用です。これは、これまで財務評価で不利になりがちだった「借入金」の一部を、会社の資産である「自己資本」として評価する画期的な仕組みです。この制度を正しく理解し戦略的に活用すれば、経審の評点を大幅に引き上げ、入札競争で優位に立つための強力な武器となります。
しかし、その活用にはメリットだけでなく、知らずにいると数年後に評点が急落する危険性がある「逓減ルール」などの重要な注意点も存在します。本記事では、経審を専門とする行政書士が、この新しい資本性借入金の制度について、評点が上がる仕組みから具体的な注意点、そしてライバルに差をつけるための戦略的な活用法まで、分かりやすく徹底解説します。
建設業の技術者資格 まるわかりガイド!
建設業における技術者資格の種類や取得方法、実務での活用法について解説。経営事項審査や入札参加に必要な資格情報を網羅しています。
2024年最新!経営事項審査(経審)完全ガイド|評点アップの戦略と改正ポイント
2024年の経営事項審査(経審)の改正ポイントや評点アップの戦略について詳しく解説。技術者要件の変更や社会性評価の拡充など、最新情報を提供しています。
経営事項審査をスムーズに進める方法!書類準備から申請まで徹底解説
経営事項審査の申請手続きや必要書類の準備方法、注意点について詳しく解説。スムーズな申請と評点アップのためのポイントを紹介しています。
建設業許可
特定建設業と一般建設業の違いとは?許可要件から判断基準まで専門家が解説
建設業許可を取得しようと調べ始めたものの、「特定建設業」と「一般建設業」という2つの区分があり、自社がどちらを目指すべきか分からずにお困りではありませんか。両者の違いが曖昧なまま許可を選んでしまうと、受注できる工事の範囲が制限されたり、将来の事業展開に影響が出たりと、後々の経営に関わる重要な問題になりかねません。
この記事では、建設業許可を専門とする行政書士が、特定と一般の根本的な違いから、具体的な許可要件、そして多くの方が誤解しがちなポイントまで、一つひとつ丁寧に解説します。
単に制度の違いを説明するだけでなく、あなたの会社の事業内容や将来のビジョンに合わせて、どちらの許可を選ぶべきかという具体的な判断基準を明らかにします。読み終える頃には、2つの許可の違いが明確に理解でき、ご自身の会社が進むべき方向性が見えているはずです。
建設業許可の全てを解説!取得から維持までの完全ガイド
建設業許可の取得から維持までの手続きを詳しく解説。許可の必要性、取得要件、申請方法、更新手続き、注意点など、建設業を営む上で欠かせない情報を網羅しています。
指名願
指名競争入札の仕組みと参加方法
指名競争入札の概要や参加方法、必要な手続きについて解説。公共工事の受注を目指す企業にとって有益な情報を提供しています。
建設業法関連
【建設業法改正】工期ダンピングの受注者禁止を完全解説!見積もりとコスト管理を変えて利益を生む方法
2020年10月に施行された改正建設業法により、「著しく短い工期」での契約が、工事を請け負う受注者側にも禁止されました。「元請からの指示だから」「これまでもそうだったから」という理由で、無理な契約を結んでいないでしょうか。その慣習が、今後は自社を法律違反という大きなリスクに晒す可能性があります。
この記事では、工期ダンピング規制の強化について、何がどう変わったのかという基本から、建設現場への具体的な影響、そして会社として今すぐ取り組むべき対策までを、全6章にわたって体系的に解説します。法改正から会社を守る守りの知識だけでなく、見積もりやコスト管理を見直して、会社の収益力を高める攻めの経営手法までを学ぶことができます。
このルール変更は、単なる規制強化ではありません。不当な価格競争から抜け出し、誠実な仕事を行う会社が正当に評価される時代への転換点です。この記事が、法改正という変化を乗りこなし、貴社の経営体質をさらに強くするための羅針盤となれば幸いです。
「コリンズって何?」中小建設業社長の疑問に答える!簡単解説&実践マニュアル
公共工事の入札に必要な建設業者情報管理システム「コリンズ」について、その概要や登録方法、活用のポイントをわかりやすく解説しています。
2025年の建設業法改正で何が変わる?中小建設会社が今すぐ知るべき実務対応
2025年施行の建設業法改正により、価格交渉の義務化やICT活用の努力義務化、主任技術者の配置基準の合理化などが導入されます。中小建設会社が取るべき実務対応について詳しく解説しています。
熊本市で浄化槽を設置するなら必見!手続き、補助金、維持管理のすべて
熊本市で浄化槽を設置・管理する際に必要な手続きや補助金制度、維持管理のポイントを詳しく解説しています。
浄化槽法に基づく管理者の義務や、熊本市独自のルール、関係機関の役割分担など、安心して浄化槽を利用するための情報が満載です。
これから浄化槽の設置を検討されている方や、既に設置済みの方も、ぜひご一読ください。
解体工事の手続きと注意点をわかりやすく解説
建物の解体工事を進める際には、押さえておくべきポイントがいくつもあります。
このページでは、解体工事の流れや必要な手続き、注意点について、わかりやすく解説しています。
中小建設業の社長必見:BIMって何?メリットから導入の壁、未来まで 徹底解説!
最近、建設業界で耳にする「BIM」という言葉。
「難しそう」「うちには関係ない」と感じていませんか?
しかし、BIMは建物の設計から施工、維持管理までを効率化する、建設業界の新しいスタンダードです。
このページでは、BIMの基本的な考え方や導入のメリット、そして中小建設業が直面する課題とその解決策について、わかりやすく解説しています。
産業廃棄物収集運搬業
【2026年改正対応】廃棄物処理法施行規則改正が建設業の経審と契約書にもたらす重大影響と対策
公共工事の受注を左右する経営事項審査(経審)と、建設工事に不可欠な産業廃棄物処理。この二つは無関係ではありません。
特に、2026年1月、そして2027年4月に施行が見込まれている廃棄物処理法施行規則の改正は、建設業者様(元請業者)が負う排出事業者責任を大きく強化します。今回の改正は、委託契約書への「第一種指定化学物質情報」の記載義務や、電子マニフェストの運用強化を求めるものです。
法令遵守が不十分であれば、行政処分のリスクが高まり、結果として経審の信頼性を損なうという重大な問題に発展しかねません。本記事では、この複雑な改正の具体的な内容と、建設業者様が今すぐ取り組むべき契約書の見直し、体制構築の対応策を、経審専門の行政書士が分かりやすく解説します。改正の波に乗り遅れず、確実な法令遵守と経審対策を実現するための道筋を示します。
建設業者が知っておくべき産廃処理の法律とリスク ~知らなかったでは済まされない
建設業における産業廃棄物処理の法律やリスクについて解説し、適切な対応方法を紹介しています。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得ガイド
産業廃棄物収集運搬業の許可取得に関する手続きや要件、注意点について詳しく解説。適切な許可取得により、法令遵守と業務の円滑な運営をサポートします。
建設業業界
【最新動向】建設業のM&Aが急増する背景と成功の鍵〜技術・人材承継と許可維持の戦略〜
日本の建設業界では、後継者不足や深刻な人手不足といった構造的な課題を解決するため、M&A(合併・買収)が最も重要な戦略的選択肢となり、件数が急速に増加しています。特に、利益が出ているにもかかわらず廃業を余儀なくされる「後継者難倒産」を防ぐための事業承継を目的としたM&Aの重要性が高まっています。
しかし、建設業のM&Aは、通常の企業買収とは異なり、建設業許可の承継や、簿外債務となりやすい未払い残業代といった業界固有のリスクを正確に評価しなければ成功しません。M&Aの成否が、企業の技術、雇用、そして公共工事の受注能力(経営事項審査の評点)に直結するからです。
この記事では、建設業の専門家である行政書士が、M&A活発化の背景、成功のための実務的な注意点、そしてM&A後の建設業許可の維持という最重要論点を徹底的に解説します。貴社が取るべき最適な事業承継戦略と、リスクを回避し、競争力を高めるための具体的な手法を学ぶことができます。
建設業者の出口戦略を徹底解説! M&A、親族・社員承継を成功に導くための全知識
この記事では、建設業の出口戦略として考えられる3つの主要なパターンを、それぞれのメリット・デメリット、そして乗り越えるべき課題まで踏み込んで徹底解説します。特に、令和2年の法改正で重要となった建設業法第17条の2・3に基づく事前認可制度や、「経営業務の管理を適正に行う体制」の整備といった専門的な要点を、具体的な準備方法とともにご紹介します。本記事をお読みいただくことで、会社の価値を最大化し、社員や取引先に安心を与える円満な引退を実現するためのロードマップが明確になります。
2025年12月施行・改正建設業法 「不当な買い叩き」が経審を直撃する? 勧告・公表リスクと実務対応を解説
2025年12月12日、改正建設業法が施行され、「不当に低い請負代金(不当な買い叩き)」への規制が本格化します。これまで「慣習」として行われてきた契約が、今後は「勧告・公表」の対象となり、会社の信用、ひいては経営事項審査(経審)の評点にも影響を与えるリスクが出てきました。
この記事では、法改正で具体的に何が変わるのか、元請企業と下請企業がそれぞれ実務でどう対応すべきか、そして最も恐ろしい「勧告・公表」のリスクについて、専門家の視点でわかりやすく解説します。
「最近、建設業界で会社の合併や買収の話をよく聞く」「後継者がいない、というニュースを見たことがある」。建設業界で、今まさにM&Aが急速に増えています。その背景には、業界全体が直面する、避けては通れない根深い課題があるからです。この記事では、なぜ建設業界でM&Aがこれほど活発なのか、その目的と仕組み、そして成功の秘訣までを、この業界の未来を担う皆さんにも分かるように、一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事が、皆さんが建設業界の今と未来を考える、一つのきっかけとなれば幸いです。
高市新総理の誕生が熊本の建設業にもたらす「事業機会」と「経営課題」の全貌
高市新総理の誕生は、公共事業を主体とする貴社にとって「千載一遇の事業機会」となる可能性があります。氏が掲げる「国土強靭化」政策は、熊本県内の公共工事を大幅に増加させ、直接的な追い風となるでしょう。
しかし、この好機は「深刻な人手不足」や「コスト高騰」といった経営リスクを加速させる諸刃の剣でもあります。
本記事では、この大きな変化の波を乗りこなし、チャンスを確実な成長に繋げるための具体的な経営戦略について、専門的な見地から詳しく解説します。
【建設DXの最前線】「業務効率化」はもう古い。AIによる「経営改革」の新常識を完全解説
「深刻化する人手不足に、待ったなしの2024年問題。従来の延長線上にある改善努力だけでは、もはや限界かもしれない」。多くの建設業経営者様が、このような強い危機感を抱いているのではないでしょうか。
解決策として「AI」が注目されていますが、「どうせ大手企業の話だろう」「具体的に何から手をつければいいか分からない」と感じている方も少なくないはずです。しかし、実は建設業におけるAI活用は、単なる「業務効率化」から、会社の未来そのものを左右する「経営改革」のステージへと、今まさに進化を遂げています。
本記事では、なぜ今AIが建設業界で急速に注目されているのかという根本的な背景から、企業の規模に応じた具体的な活用事例、そしてAIがもたらす未来の現場までを網羅的に解説します。さらに、AI導入で失敗しないための「目的の決め方」や「賢い始め方」まで、経営者が本当に知りたい情報を凝縮しました。
AIは、遠い未来の技術ではありません。貴社の未来を拓く「優秀なアシスタント」としてどう向き合うべきか、この記事からその答えを見つけてください。
【2025年版】建設業界の最新市場動向を徹底分析!中小企業が取るべき経営戦略とは?
2025年の建設業界の市場動向を分析し、中小企業が取るべき経営戦略や対応策について提案しています。
CCUS導入で会社が変わる!メリット・登録方法・経審活用術を専門家が解説
建設キャリアアップシステム(CCUS)の導入によるメリットや登録方法、経営事項審査への活用方法について専門家が詳しく解説しています。
2024年12月からルール改正!主任技術者・管理技術者の配置基準を徹底解説
2024年12月から改正される主任技術者・管理技術者の配置基準について、その内容や実務への影響を詳しく解説しています。
2025年、建設現場が止まる!? 熊本の建設業を支えるために今できること
2025年を境に、ベテランの技術者や現場の職人たちが一斉に引退する可能性が高く、それにより人手と技術が一気に失われるリスクが高まっているという状況です。特に熊本のように地元に根ざして事業を展開している中小建設会社にとって、この問題は経営の根幹を揺るがしかねない深刻な課題といえます。
建設業は政治に左右される?予算と政策のリアルな関係
建設業界が政治的な判断や空気感で公共工事予算が大きく揺れ動いた結果、深刻な影響を受けてきた歴史を解説。今後も同じ過ちを繰り返さないためには、科学的・現実的な視点で必要な予算を確保し続ける姿勢が求められます。
〖熊本版〗一級建築士事務所 開業への道!登録申請の全ステップ徹底ガイド
一級建築士として独立を目指す方へ、建築士事務所の登録手続きは避けて通れない重要なステップです。
このガイドでは、熊本県での登録申請の流れや必要書類、注意点をわかりやすく解説しています。
信頼される建築士事務所としての第一歩を踏み出すために、ぜひご一読ください。
熊本県建設産業の未来を読み解く:第4次振興プランの全貌
熊本県の建設業界が直面する課題とチャンスを捉えた「第4次建設産業振興プラン」。
人材不足や高齢化、働き方改革、そして半導体産業の集積による新たな需要など、地域特有の背景を踏まえた戦略が描かれています。
このページでは、熊本県の建設業が持続的に発展するためのビジョンと具体的な取り組みを詳しく解説しています。
2025年の建設業界予測:資材価格・労務費・制度改正の動向まとめ
建設業界に大きな影響を及ぼす「資材価格」や「労務費」の最新予測に加え、2025年に向けた主要な制度改正情報を整理。
お金のこと
建設業のための「省エネルギー投資促進補助金」完全活用ガイド|初期投資負担を減らし、会社の利益と経審を伸ばす
「省エネ設備を入れたいけれど、初期投資が高くて踏み切れない」「国の補助金は複雑で、採択される自信がない」—建設業を経営する皆様が抱える、こうした課題を解決する方法があります。
近年、建設会社にとって省エネルギーへの取り組みは、単なる環境対策ではなく、将来の受注(入札)や経営事項審査(経審)の評価に直結する重要な経営戦略となっています。国もCO2排出量削減を急務とし、高効率設備への更新を支援する各種補助金(省エネ投資促進補助金など)に毎年大きな予算を割いています。
本記事では、建設業の皆様が直面するエネルギー課題から、複雑な補助金制度の仕組み、事務所や工場で活用できる具体的な設備、そして補助金活用によっていかに経審の評価に間接的に良い影響を与えられるかまでを、行政書士の視点から徹底的に解説します。採択を勝ち取るための緻密な「省エネ計算」の重要性や、資金繰りの注意点など、貴社が確実に補助金を獲得し、経営基盤を強化するための具体的な手順をお伝えします。
ものづくり補助金 採択事例集:建設会社がDX・省人化で競争力を高めた成功パターン
「ものづくり補助金」は、高額な設備投資の初期負担を軽減し、建設会社の生産性を飛躍的に向上させるための鍵です。しかし、申請にあたり「具体的にどのような設備や取り組みが採択されるのか」という疑問をお持ちの経営者様は多いのではないでしょうか。本記事では、建設DX、省人化、ニッチ市場開拓といった主要な分野で、実際に補助金を活用して成功した建設会社の具体的な事例を徹底的に解説します。成功した事業計画の共通点や、採択の鍵となったロジックを事例から学び、貴社が取り組むべき次世代の設備投資戦略を見つけ出しましょう。
建設業のためのIT導入補助金活用ガイド【2025年版】申請方法から採択のコツまで分かりやすく解説
人手不足や働き方改革への対応、そして止まらない物価の高騰。多くの建設会社の経営者の皆様が、今まさにこうした厳しい経営課題に直面されていることと思います。これらの課題を乗り越え、会社を未来へつなぐための鍵となるのが「ITの活用」、つまりデジタルトランスフォーメーション(DX)です。
しかし、ITツール導入には少なくない費用がかかるのも事実です。「必要性は分かっているが、なかなか投資に踏み切れない」。そんな悩みを抱える建設会社にとって、非常に心強い味方となるのが、国がITツール導入費用の一部を補助してくれる「IT導入補助金」です。最大で450万円もの補助が受けられるこの制度を、活用しない手はありません。
この記事では、建設業を専門とする行政書士が、IT導入補助金の制度の全体像から、建設業での具体的な活用事例、採択率を上げるための事業計画の作り方、そして申請で失敗しないための注意点まで、7つの章にわたって網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、IT導入補助金を活用して会社の未来を切り拓くための、具体的で実践的な知識がすべて手に入ります。
建設業のための「ものづくり補助金」活用ガイド 採択事例と申請のコツを解説
「深刻な人手不足を解消したい」「現場の生産性を上げて、もっと利益を出せる会社にしたい」多くの建設会社の経営者が、このような課題に日々向き合われています。その解決策の一つとして国の補助金を検討する中で、「ものづくり補助金」という言葉を耳にしたことはないでしょうか。しかし同時に、「『ものづくり』という名前だから、私たち建設業には関係のない制度だ」と、最初から選択肢の外に置いてしまってはいないでしょうか。
もしそうであれば、会社の成長の大きなチャンスを逃してしまっているかもしれません。実はこの補助金、ICT建機やドローンの導入、自社独自の施工管理システムの開発といった、建設業の課題を解決し生産性を飛躍的に高めるための投資に活用され、多くの採択事例が生まれています。
この記事では、建設業を営む皆様に向けて、ものづくり補助金の基本的な仕組みから、具体的な採択事例、そして申請でつまずかないための重要なポイントまでを、専門家の視点から一つひとつ丁寧に解説します。貴社の未来を拓くヒントが、ここにあります。
2025年の建設業法改正で何が変わる?中小建設会社が今すぐ知るべき実務対応
2025年施行の建設業法改正により、価格交渉の義務化やICT活用の努力義務化、主任技術者の配置基準の合理化などが導入されます。中小建設会社が取るべき実務対応について詳しく解説しています。
建設業の資金繰りに効く!ファクタリングの正しい使い方
建設業特有の資金繰り課題を解決する手段として注目されるファクタリングの仕組みや活用方法、注意点について、実務的な視点から詳しく解説しています。
建設業の資金繰りを改善するための資金調達方法
建設業における資金繰りの改善策として、ファクタリングや融資、補助金・助成金の活用方法など、さまざまな資金調達手段を紹介し、それぞれのメリット・デメリットを解説しています。
設計労務単価とは?建設業における人件費の基準を解説
公共工事における人件費の基準となる設計労務単価について、その概要や算出方法、実務への影響などを詳しく解説しています。
建退共制度の概要と加入手続き
建設業退職金共済制度(建退共)の概要や加入手続き、メリットについて解説。労働者の福利厚生向上と企業の信頼性向上に役立つ情報を提供しています。
小規模事業者持続化補助金の申請から採択までを徹底解説
新たな取り組みや業務効率化を図りたいとお考えの際、資金的な準備が必要となります。
このページでは、国が提供する「小規模事業者持続化補助金」の制度について、申請から採択までの流れや注意点をわかりやすく解説しています。
自社の成長を支援するための一助として、ぜひご活用ください。
建設業会計の教科書、なぜ、あなたの会社は儲かっているのに現金がないのか?
建設業特有の会計処理は、一般的な企業とは異なる勘定科目や工事進行基準など、独自ルールが多数存在します。
このページでは、建設業会計の基本概念から、収益認識の仕組み、実務に使える会計制度対応までをわかりやすく整理しました。
経理担当や事業者の方が「何をどう処理すればいいのか」をすぐに理解できる構成です。
お知らせ
熊本市「企業立地促進補助金」徹底解説|対象・補助率・要件・相談時の注意点まとめ
熊本市では、製造・物流関連産業や情報通信関連企業、本社機能の移転・拡充を支援するため、手厚い企業立地促進補助制度を設けています。土地取得費・賃料・設備投資・雇用に対する支援が用意されており、初期投資の負担軽減や事業展開のスピード向上につながる可能性があります。本記事では、公開情報に基づき制度の概要を整理するとともに、補助率・上限額・主な要件・活用時の注意点をわかりやすくまとめています。検討段階から早期の事前相談が求められる制度のため、計画立案の参考情報としてご活用ください。
ものづくり補助金、申請を考える前に知っておきたい5つの意外な事実【公式データ徹底分析】
ものづくり補助金は、中小企業の設備投資や新サービス開発を後押しする強力な支援制度です。しかし、採択率は決して高くなく、申請のタイミングや枠の選択、事業計画の精度によって結果が大きく変わることをご存じでしょうか。
本記事では、公式データをもとに「採択率」「応募社数の推移」「枠別採択状況」「累計支援規模」「制度特有のルール」という5つの観点から、申請前に押さえておくべき重要ポイントを解説します。公募要領の読み込みだけでは分からない、実務的な視点から分析した内容です。
これからものづくり補助金に挑戦しようと考えている方が、戦略的に準備を進めるための指針としてご覧ください。
【第13次公募開始】事業承継・M&A補助金 (2025/11/28締切) | 上限2,000万円特例あり
中小企業者・小規模企業者の皆様、事業の存続・発展に欠かせない支援策が始まります。中小企業庁所管の**「事業承継・M&A補助金(第13次公募)」**の申請受付が、2025年10月31日より開始されました。本補助金は、親族内承継、従業員承継、M&Aに伴う専門家活用、M&A後のPMI、さらには廃業・再チャレンジに至るまで、幅広いステージの経営変革を強力に後押しします。
公募締切は2025年11月28日(金)17:00と短期間です。特に、補助上限額や補助率は申請する「枠」や「類型」によって大きく異なり、条件付きで上限2,000万円の特例が適用される枠もあります。申請を検討されている方は、ご自身の状況と照らし合わせて最適な枠を選ぶ必要があります。
本記事では、公募期間、補助金の4つの枠の概要、補助上限額と補助率の注意点、そして申請に必須となるGビズID取得の最新目安時間など、第13次公募で押さえておくべき重要ポイントを解説します。期限が迫っていますので、お早めに詳細をご確認ください。
知らないと出遅れる?令和8年度「日本芸術文化振興会」助成金の最新ポイントまとめ
令和8年度の日本芸術文化振興会による助成募集が始まり、芸術文化活動を行う個人や団体にとって重要な申請シーズンが到来しました。本記事では、公式情報を踏まえつつ、スケジュール、制度の違い、対象分野、年度ごとの変更点、準備すべき資料といった「特に押さえておきたい要点」をわかりやすく整理しています。応募検討中の方は、早期準備と最新案内の確認にぜひお役立てください。
太陽光パネルの「その後」を知っていますか?政府の動きから見える3つの重要な視点
太陽光パネルはクリーンエネルギーの象徴として全国に広がっています。しかし、将来寿命を迎えるパネルをどのように循環させるのかという課題は、まだ十分に知られていません。本記事では、NEDOが公表した研究開発公募予告をもとに、使用済み太陽光パネルのリサイクルに向けた国の最新の取り組みと、その背景にある3つの重要な視点をわかりやすく解説します。持続可能な社会づくりに欠かせない「太陽光パネルのその後」に注目してみましょう。
IT導入補助金2025、採択率の現実は?公式データから見えた5つの意外な事実
IT導入補助金は、中小企業にとってDX推進の重要な資金調達手段ですが、申請すれば必ず採択されるわけではありません。本記事では、2025年度の公開データや公式交付決定情報をもとに、採択率の傾向や類型ごとの差異、申請タイミングによる影響などを整理します。断定できない要素や未公表部分には注意しつつ、実務で参考になる「競争環境としてのIT導入補助金」を捉える視点を提供します。申請を検討している企業が、戦略的に準備を進めるためのヒントとしてご活用ください。
「補助金の上限なし!?」知らなきゃ損する、令和7年度「資源循環システム補助金」の意外なポイント5選
GX(グリーン・トランスフォーメーション)やサーキュラーエコノミーの重要性が高まるなか、国の資源循環システム補助金(令和7年度)は、従来型の補助金を超える柔軟性と支援規模が特徴とされています。本記事では、公募情報に基づき「補助上限なし」の制度設計や、製品ライフサイクルを通じた幅広い支援範囲、事前申請・事前着手などのポイントを整理。次回公募に向け、企業が押さえるべき戦略視点をわかりやすく解説します。
データで読み解く建設業の現在地:投資の二極化と資材需要の回復基調が示す「次の一手」
国内の建設市場では、住宅・民間投資の慎重姿勢が続く一方、公共・インフラ分野は底堅さを維持するという「投資の二極化」が鮮明になりつつあります。さらに、主要建設資材の需給バランスは徐々に安定に向かい、回復基調を示す品目も見られます。こうしたデータが示すのは、従来の強みだけでは持続的成長を描きにくい環境が到来しているという現実です。いま、中小建設企業が注視すべき市場の変化と、次の戦略的アクションとは何か。最新の経済指標をもとに、未来の競争優位をつくる視点を整理します。
知らなきゃ損!熊本市の「高齢者住宅バリアフリー化」補助金、3つの意外なポイント
熊本市では、高齢者が安心して暮らせる住まいづくりを支援する「高齢者住宅バリアフリー化改修費補助金」を実施中。介護が必要になる前の“予防リフォーム”を支援する意外な制度です。対象条件や補助額、申請の注意点をわかりやすく解説します。
「緑地」は単なる美観ではない。国交省「TSUNAG認定」が示す建設業の新たな企業価値とは?
国土交通省が進める「TSUNAG(ツナグ)認定」は、きれいな外構づくりを評価する制度ではありません。気候変動対策、生物多様性、そして人が安心して過ごせる空間づくりといった観点から、企業や開発プロジェクトが計画的に確保・維持する緑地を国が認定する仕組みです。これは、建設業の価値が「どれだけ造ったか」だけではなく、「地域と環境にどんな価値を残したか」でも評価される流れが本格化してきたことを示します。いまや緑はコストではなく、企業ブランド・信用力・受注力につながる“経営資産”になりつつあります。その背景と現場への影響を、事例とあわせて解説します。
雇用関係助成金の申請を検討している中小企業の方へ。2023年度以降、厚生労働省による制度見直しで「生産性要件の廃止」や「登記事項証明書の提出不要化」など、手続きが大きく変わっています。本記事では、申請負担を軽減する3つの最新ポイントと、注意すべき詐欺的勧誘の実例を専門家がわかりやすく解説します。
【熊本移住者必見】中古住宅補助金で最大50万円!申請前に知るべき3つの注意点
熊本市への移住や住み替えを考えている方に朗報です。
市では、県外からの移住者や市内転居者を対象に、中古住宅購入費の一部を最大50万円まで補助する制度を実施しています。
ただし、この制度には「契約の前に申請」「先着わずか約20件」「転入後3年以内も対象」など、見落とすと損をする重要なルールが存在します。
この記事では、熊本市の公式情報をもとに、補助金申請で失敗しないために知っておくべき3つの落とし穴をわかりやすく解説します。
「BIM審査」は建設業の未来をどう変えるか?〜AI・ICTが塗り替える現場の「当たり前」と、生き残る企業の条件〜
来春から始まる「BIM審査」は、建設業界の仕事の進め方を根本から変える可能性があります。
「また新しい制度か…」と感じる方も多いかもしれませんが、これは単なる手続き改革ではなく、
設計・施工・検査のすべてをデジタルでつなぐ“新しい時代の入口”です。
AIによる出来形検査や、光ファイバーで地盤を常時監視する技術など、現場の「当たり前」は今まさに塗り替えられようとしています。
この変化を「面倒な規制対応」として終わらせるのか、それとも「未来をつくるチャンス」として掴むのか。
この記事では、BIM審査の導入がもたらす変革と、デジタル時代に生き残るための条件を、行政書士の視点から解説します。
「賃上げ」だけでは解決しない建設業の本質的な課題:アナリスト行政書士が読み解く「20,724円」の裏側
建設業の平均賃金改定額が20,724円に――。厚生労働省の令和7(2025)年調査で示されたこの数字は、全産業平均を約7,100円も上回り、業界全体が「人への投資」を本格化させている現実を映し出しています。しかし、喜ばしいニュースの裏側には、価格転嫁の難しさや生産性改革の遅れといった、根深い構造課題も存在します。本稿では、行政書士兼アナリストの視点から、この“20,724円”が意味する真のメッセージを読み解き、持続可能な経営への道を探ります。
「事業承継・M&A補助金」と聞くと、申請書を提出して採択を待つだけの制度――そんな印象を持っていませんか? しかし、公式サイトの「お知らせ」欄を丁寧に読み解くと、そこには制度の変化や政策意図、採択傾向、そして思わぬチャンスの兆しまで隠されています。 本記事では、表面的な申請ノウハウを超えて、補助金制度の“裏側”を読み解くための5つの戦略的視点を紹介します。 補助金を「申請する側」から「戦略的に活用する側」へ――一歩先を行く経営判断のヒントをお届けします。
【2025年後半】「また値上げか…」で終わらせない。資材高騰時代を生き抜く建設業者のための”契約”という最強の盾
円安、エネルギー高、そして止まらない資材価格の上昇——。
2025年後半の今、建設業界はかつてないコスト圧力にさらされています。
「仕方ない」「我慢するしかない」では、もう会社を守れません。
この記事では、赤字工事を防ぎ、自社の利益を守り抜くために知っておきたい“契約の見直し”と“交渉の知恵”を、実践的に解説します。
契約こそ、あなたの会社を守る最強の盾になるのです。
「うちには関係ない」ではもう済まない。建設業界の未来を握る『脱炭素技術』という名の静かな革命
「脱炭素」や「カーボンニュートラル」と聞いて、「自分たちには関係ない」と感じていませんか?
しかし今、その考えは危険信号です。大林組がCO₂排出量を67%削減した新技術「クリーンクリート®」を発表するなど、大手ゼネコンが次々と“環境技術”に巨額投資を進めています。
これは単なるCSRやイメージ戦略ではなく、発注を勝ち取るための「経営戦略」であり、今後の建設業界を根底から変える“静かな革命”の始まりです。
「土曜も現場」は、もう誰のためにもならない。データが暴く週休2日の壁と、発注者に「ノー」と言う勇気
「また今週も、土曜出勤か…」。
国交省の最新調査(2025年10月14日発表)によれば、建設現場で「完全週休2日」を実現できているのは、わずか3割に過ぎません。
2024年の時間外労働規制から1年半、業界全体で“働き方改革”が叫ばれる一方で、現場の休日は依然として遠い理想のまま。
この記事では、なぜ「休めない」のか、その背景にある構造的課題をデータで解き明かし、現場が発注者に「ノー」と言えるための3つの武器──交渉力・DX・適正見積もり──について解説します。
熊本市で庭木を植えるなら必見!知らなきゃ損する「森づくり補助金」の意外な落とし穴と賢い活用法
熊本市で庭や店舗まわりを緑で彩りたい方へ。
市が樹木の購入費や植え付け費用を助成してくれる「つながりの森づくり補助金」は、個人でも事業者でも活用できるお得な制度です。
ただし、申請のタイミングや補助額の計算方法など、知らないと損するポイントがいくつかあります。
この記事では、失敗を防ぎ、補助金を最大限に活かすための4つの重要ポイントをわかりやすく解説します。
熊本市への事業拠点設立のご提案:成長とイノベーションを加速する戦略的選択
九州の中心・熊本市は、空港・新幹線・港湾の三位一体アクセス、理工系人材の安定供給、そして全国トップクラスの企業立地補助で、成長投資のリターンを最大化できる都市です。本提案では、拠点設立におけるコスト最適化、人材獲得、半導体を軸とした産業エコシステムの活用まで、貴社の意思決定に直結する要点をコンパクトに整理しました。
熊本の地域を緑でいっぱいに!意外と知らない「緑の募金」助成金、5つの重要ポイント
熊本のまちをもっと緑豊かにしたい――そんな想いを形にできる制度が「緑の募金」助成金です。
最大300万円の資金支援が受けられるこの制度は、植樹だけでなく、文化財保全や学校の環境教育など幅広い活動が対象。事前相談のコツや申請の注意点を押さえれば、あなたの地域プロジェクトも実現の第一歩を踏み出せます。この記事では、申請前に知っておきたい5つの重要ポイントを分かりやすく解説します。
熊本市で空き家リフォームを考えている若者・子育て世帯必見!補助金申請前に知っておきたい意外な5つのポイント
古くなった空き家をリフォームして、理想のマイホームを手に入れたい――そんな夢を応援する制度が熊本市にあります。「空き家リフォーム促進事業補助金」は、若者世帯や子育て世帯を対象に、最大40万円の支援が受けられるチャンスです。ただし、制度には“申請のタイミング”や“対象工事の条件”など、意外と知られていない注意点がいくつもあります。この記事では、補助金を無駄にしないために知っておきたい5つの重要ポイントを、専門家の視点からわかりやすく解説します。
【最新】事業承継・M&A補助金 次回公募に向けた準備チェックリスト
事業承継・M&A補助金の直近締切は終了済み。次回公募に備えて、事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠・廃業再チャレンジ枠の要点と、賃上げ要件や上限・補助率、対象外経費、申請フローをチェックリスト形式で解説します。
中小企業成長加速化補助金とは?採択率16.6%の狭き門を突破するための最新分析【2025年版】
2025年、新たに創設された「中小企業成長加速化補助金」は、最大5億円(補助率1/2)という大型支援が受けられる、中小企業向けの“成長投資”補助金です。
対象は売上高10億円以上100億円未満の企業に限定され、「100億宣言」の公表が必須という意欲的な制度設計。
第1次公募の採択率はわずか16.6%にとどまりました。
この記事では、採択企業の特徴、投資比率・賃上げ目標など最新データをもとに制度の実態を解説します。
次回公募に向けて戦略的に備えるための必読ガイドです。
【2025年版】省力化投資補助金の最新動向|採択率・補助上限・申請戦略をわかりやすく解説
人手不足、コスト上昇、賃上げ対応――。
中小企業が直面する三重苦を乗り越える切り札として注目されるのが「省力化投資補助金」です。
本記事では、2025年最新の公募情報や採択率、カタログ注文型と一般型の違い、申請戦略、そして経営改善への活かし方までを、実務者目線でわかりやすくまとめました。
補助金の「使い方」次第で、あなたの会社の生産性は確実に変わります。
夏の小休止は終わり。静かに忍び寄る「コスト再上昇」の現実と経営者の備え
建設資材の価格が一時的に落ち着いた夏が終わり、再び「コスト上昇」の兆しが見え始めています。建設物価調査会の最新データでは、資材価格や労務費がわずかに上昇。円安や国際市況の影響も重なり、利益を圧迫する要因が静かに広がりつつあります。この記事では、データが示す最新の動きと、今後の経営判断に必要な視点—価格交渉力・データ分析力・持続可能な賃上げ対応—について解説します。
【2025年度版】地域企業経営人材確保支援事業(Re-Career給付金)|経営人材採用を支援する新制度ガイド
経営人材の確保が企業の成長を左右する時代。
経済産業省と地域経済活性化支援機構(REVIC)が運営する「地域企業経営人材確保支援事業(Re-Career給付金)」は、地方の中堅・中小企業が外部から経営層人材を採用する際に、その費用の一部を支援する制度です。
採用形態に応じて最大450万円が給付され、事業承継・経営改革・DX推進など、企業の中核を担う人材登用を後押しします。
この記事では、2025年度の最新内容・給付額・申請手順・活用のポイントをわかりやすく解説します。
【2025年度版】中堅・中小成長投資補助金|建設業DX・設備投資を支援する大型補助制度
国の重点政策として注目を集めている「中堅・中小成長投資補助金」。 2025年度も、建設業をはじめとする中堅・中小企業の設備投資・DX投資・人材投資を後押しする大型補助金として継続実施される見込みです。 工場や倉庫の新設、最新設備の導入、ソフトウェア開発など、投資規模10億円以上のプロジェクトが対象となり、最大で50億円の補助を受けられる可能性もあります。 本記事では、2025年度版の最新動向、採択率の推移、対象経費、そして申請準備のポイントをわかりやすく解説します。
神戸からキーウを動かす時代へ。国交省デモが示す建設DXの現実と未来
2025年10月9日、国交省による実証デモンストレーションで、神戸から遠くウクライナ・キーウの重機を遠隔操作する実験が行われました。
かつてSFの世界だった「遠隔施工」が、いま現実に動き始めています。この記事では、建設DXの最前線と、その導入を後押しする「IT導入補助金」の活用方法についてわかりやすく解説します。
建設業に忍び寄る「人手不足格差」──68%が仕事を断るという現実の裏で何が起きているのか
建設業界では「人手不足」が日常の言葉になって久しいですが、今、より深刻な問題が静かに進行しています。それは「人がいない」ことよりも、「採用すらできない企業」と「賃上げできる企業」との間に広がる“見えない格差”です。
2025年10月、クラフトバンク社の最新調査で、中小建設企業の68%が「人手不足で仕事を断った」と回答しました。この数字は、もはや一部の会社の悩みではなく、業界全体を揺るがす構造的リスクの警鐘といえます。
この記事では、最新データをもとに「採用格差」と「賃上げ格差」という2つの視点から、現場のリアルと経営への影響を読み解きます。
【2025年度版】熊本市DX環境整備事業補助金の公募案内と申請の流れをわかりやすく解説!
熊本市では、デジタル化を進めたい中小企業や個人事業主を応援するため、令和7年度(2025年度)も「DX環境整備事業補助金」の公募を実施しています。
この補助金を活用すれば、会計ソフトの導入やオンライン販売の仕組みづくり、デジタル人材の育成など、DXへの第一歩をサポートしてもらえます。
この記事では、公募の目的や対象者、申請方法、注意点までを初心者にもわかりやすく解説。
「うちの会社も対象かな?」「どんな準備が必要?」といった疑問に答えながら、申請までの流れを丁寧に紹介します。
デジタル化で業務を効率化したい方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
新事業進出補助金の採択率は約37%|第1回結果と次回申請の3つの攻略ポイント
新事業進出補助金の第1回公募結果が発表され、採択率はおよそ37%前後となりました。 「3社に1社は通る」とも言える一方で、業種や投資規模によって採択の難易度は大きく変わります。 さらに、この補助金は設備投資だけでなく建物費や広告宣伝費まで幅広く対象になるのが特徴です。 本記事では、第1回の結果から見えた3つの戦略ポイントを解説し、次回申請での成功につなげるヒントをお届けします。
相次ぐ大手ゼネコンのM&Aは、単なる業界ニュースではなく、日本の建設業界全体が構造的な変革期に突入したことを示す重要なシグナルです。この地殻変動は、元請けと協力会社の関係性を根底から見直す動きに直結します。これまでのような慣習や価格交渉力だけでなく、企業の技術力、財務の安定性、そしてコンプライアンス体制といった「総合力」が客観的なデータに基づいて評価され、取引先が選別される時代が本格的に到来します。
この大きな変化の波を、単なるリスクとして傍観するのか、それとも自社の経営体質を強化し、他社との差別化を図る好機と捉えるのか。その分水嶺は、現状を正しく分析し、具体的な次の一手を打てるかどうかにかかっています。
本レポートでは、この業界再編の深層にある構造的要因の分析から、今後協力会社に求められる具体的な評価基準の予測、そして「経営事項審査データ」という客観的指標を活用した経営改善計画の策定まで、貴社が「選ばれ続ける」ための戦略を全5章で体系的に解説します。
2025年参議院選挙後の建設業界:ねじれ国会と構造課題を乗り越える戦略
2025年7月20日の参議院選挙は、日本政治に「ねじれ国会」を再来させ、建設業界の未来にも大きな影響を与えます。働き方改革や人手不足、資材価格高騰など、業界が抱える構造的課題に対し、この政治変動がどう作用するのか。本記事では、選挙結果が公共事業や国土強靭化計画、各政党の政策、そして業界のDX推進に与える影響を分析し、建設企業の皆様が持続可能な成長を実現するための戦略を提示します。
建設業許可業者数、2年連続で増加!国土交通省発表から読み解く業界の今
国土交通省が発表した令和6年度末の建設業許可業者数は、前年より4,317業者増の483,700業者となり、2年連続の増加となりました。
この増加は、インフラ整備の需要増加や事業承継の促進など、建設業界の活性化を示しています。
このページでは、最新データの詳細や増加の背景、建設業許可の意義について詳しく解説しています。
2025年度「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」閣議決定のお知らせ
2025年4月22日、政府は官公需法に基づき、2025年度の「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定しました。
この方針では、近年のコスト増加を踏まえ、中小企業との適正な価格での契約を推進するため、価格交渉や価格転嫁の円滑化が盛り込まれています。
また、複数年度契約においては、受注者の申し出がなくても、年1回以上の契約金額の見直し協議を行うことが定められました。
令和7年度 熊本県建設産業 働き方改革推進事業費補助金のご案内
熊本県では、建設業界の人材確保や働き方改革を支援するため、令和7年度の補助金制度を実施しています。
ICT導入や時間外労働の削減、労働力の確保、処遇改善など、多岐にわたる取り組みが補助対象となります。
申請期限は2025年6月17日(火)まで。詳細な要件や申請方法については、上記リンクからご確認ください。
2025年5月倒産レポート解説:なぜ倒産は減ったのか?そして、これから何をすべきか?
【数字の裏を読む力】「倒産17.4%減」の“朗報”に潜む、本当の危機とは
2025年5月、建設業界に「倒産17.4%減」という一見明るいニュースが報じられました。ですが、その数字に安心するのは、少し早いかもしれません。なぜならその減少は、前年の異常値との比較による“錯覚”であり、業界の足元ではいま、かつてない規模の地殻変動が進行中だからです。
本記事では、「なぜ倒産が減ったのか?」という素朴な問いから出発し、見落とされがちな統計の落とし穴や、建設業界が直面する4つの構造的危機――「2024年問題」「人材不足」「物価高」「ゼロゼロ融資返済」――を徹底的に掘り下げます。さらに、その嵐が特に中小・零細企業に与える影響や、未来を生き抜くための3つの処方箋までを丁寧にお伝えします。
建設業の“現在地”と“これから”を見極めたいすべての方に――。
数字の表層ではなく、本質を見抜くためのヒントがここにあります。