実践まちづくりファシリテーション講座
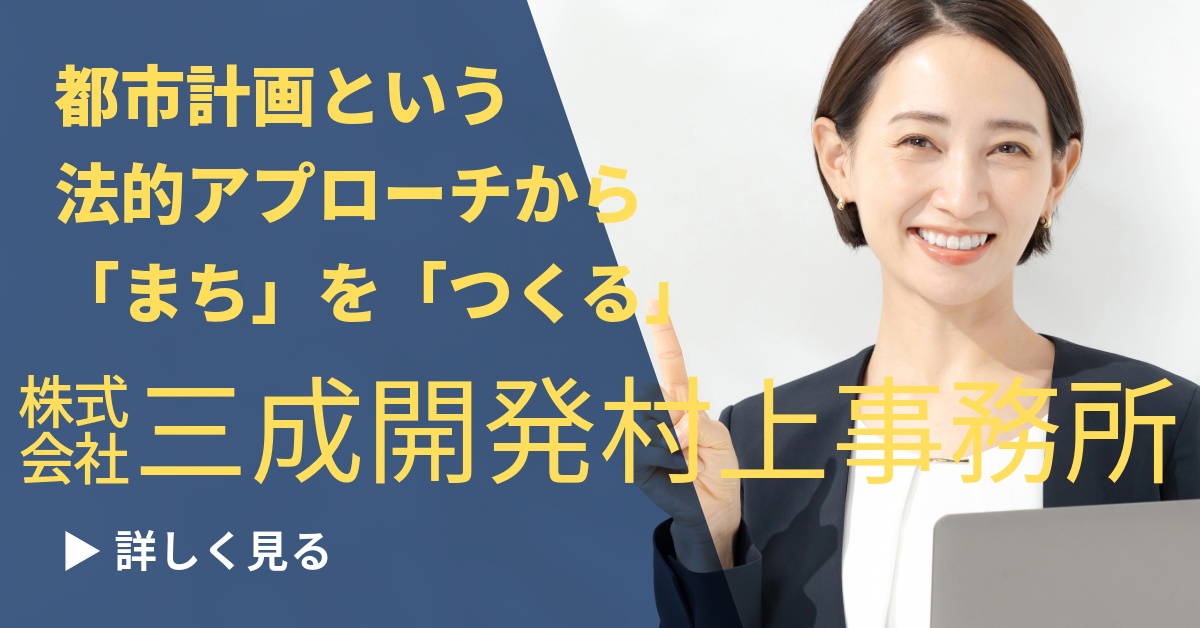
実践まちづくりファシリテーション講座:【実践講座】シリーズ
もう「調整」で疲弊しない。厄介な“反対意見”を宝の山に変える、新しい合意形成の教科書
「市民のため」という熱意とは裏腹に、終わらない調整と合意形成の難しさに、心がすり減っていませんか。実はその行き詰まりの原因は、異論のない「全員賛成」の会議にこそ潜んでいます。良かれと思って見過ごした小さな声が、やがてプロジェクト全体を揺るがす大きなリスクに育つのです。
本記事では、なぜその悲劇が起きるのかを解き明かし、厄介な「対立」をプロジェクトの「推進力」に変える、実践的な対話の技術を解説します。
もう「調整」で疲弊するのは終わりです。反対意見の中から「宝」を見つけ出し、地域の未来を創造する「合意形成の専門家」への第一歩を、ここから踏み出しましょう。
NPOと行政の「協働」がうまくいかない本当の理由:善意だけでは埋まらない構造的ギャップを乗り越える
「地域のために」。その高い志で始めたはずのNPOとの協働事業。なのに、なぜか会議はいつも重苦しく、話は噛み合わない。「想いはわかるが、ルール上…」「行政は動きが遅い」。そんな言葉の応酬に、心がすり減っていませんか?
もし、あなたが「自分の調整能力が低いせいだ」と一人で悩んでいるなら、この記事を読んでください。その「うまくいかない」根本原因は、あなた個人の能力の問題では決してありません。それは、NPOと行政との間に横たわる、見過ごされがちな「文化」と「時間」に関する、あまりにも大きな「構造的ギャップ」に起因しているのです。
この記事では、長年の行政現場で見てきた数々の失敗事例を基に、そのギャップの正体を徹底的に解き明かします。そして、ただ問題点を指摘するだけでなく、その困難な壁を乗り越え、辛い「“協”働」を、新しい価値を生み出す「協創」へと転換するための、具体的で実践的な「ファシリテーション」という名の処方箋をあなたにお渡しします。
もう、板挟みで悩むのは終わりにしましょう。この記事を読み終えた時、あなたは明日からの仕事に自信と希望を取り戻し、目の前の霧が晴れるような感覚を得られるはずです。
なぜ専門家のアドバイスは住民に響かないのか?「専門性の罠」を乗り越える対話術
なぜ、完璧な説明ほど住民の心を遠ざけてしまうのか。なぜ、あなたの熱意は空回りしてしまうのか。そのもどかしさの原因は、能力や情熱の問題ではありません。専門家が無意識に陥る「見えない罠」と、住民との埋めがたい「視点の違い」にあります。
この記事は、その根本的な構造を解き明かし、一方通行の「説明」を、信頼を生む双方向の「対話」へと転換するための、具体的な技術を伝えるものです。
あなたの持つ専門知識と情熱を、今こそ本当に地域のために役立てるために。共にその第一歩を踏み出しましょう。
住民参加ワークショップが「お遊戯」で終わる5つの理由とその処方箋
「たくさんの付箋、活発に見える議論…。なのに、なぜか心に残るのは『結局、何も決まらなかった』という徒労感だけ。」
地域のためにと始めたはずの「住民参加ワークショップ」が、いつしか参加者と行政の双方にとって、アリバイ作りのための「お遊戯」になっていませんか。
その原因は、あなたの熱意や能力不足ではありません。実は、多くの真面目な行政職員が見落としている、構造的な「5つの落とし穴」に潜んでいるのです。
この記事では、長年まちづくりの合意形成に携わってきた専門家が、ワークショップが失敗に終わる根本的な理由を徹底解剖。さらに、明日からすぐに現場で使える具体的な「5つの処方箋」を、豊富な経験に基づいて詳しく解説します。
「やった感」だけの虚しい会議から脱却し、多様な住民と「本気の対話」を生み出し、確かな成果へと繋げるための、プロとしての自信と技術を手に入れてください。
実践まちづくりファシリテーション講座:【完全ガイド】シリーズ
熱意が空回りしない!空き家活用を導くワークショップ設計マニュアル
「この空き家、どうにかならないかな……」
商店街の一角でシャッターが閉まったままの店舗、かつて賑わっていた住宅地に取り残された古民家。まちづくりに関わる方なら、きっと誰もが一度はそんな風に考え、心を痛めたことがあるのではないでしょうか。
行政として、素晴らしいアイデアや熱い想いがあっても、いざ動き出すと、関係者の意見調整、法務手続きの壁、そして何より住民の「本当にうまくいくの?」という不安の声に、なかなか前に進めないのが現実です。
この記事では、そうした課題を乗り越え、空き家・空き店舗活用プロジェクトを成功に導くための実践的な手法として、「ワークショップ」の設計と活用方法を解説します。ただのアイデア出しで終わらせない、関係者全員が「自分たちのまちの未来」として捉え、自律的に動き出すためのロードマップを、私たちと一緒に描いていきましょう。
実践まちづくりファシリテーション講座:【深掘り解説】シリーズ
「リーダーシップを発揮しろ」と言われて途方に暮れるあなたへ。ファシリテーションこそが、現代のリーダーに必須の最強スキルである理由
なぜあなたの「正論」が響かないのかという根本原因から、多様な意見を「合意」へと導くファシリテーションの本質、そして両者を組み合わせた「ファシリテーター型リーダー」という新しい時代のリーダー像までを、具体的な事例と共に徹底解説します。
読み終える頃には、あなたを縛り付けていた「リーダーシップ」という言葉の重圧から解放され、明日からの会議や住民説明会に、自信と希望を持って臨めるようになっているはずです。さあ、あなたを苦しめる『古い地図』を手放し、仲間と共に未来を創る『新しいコンパス』を手に入れる旅へ出発しましょう。
まちづくり
「また新しい交付金か…」その”うんざり感”の正体とは? デジ田交付金(TYPE-S)で本当に向き合うべきこと
「また国から新しい交付金が…」その”うんざり感”、痛いほど分かります。しかし原因は、あなたの能力不足ではありません。
この記事では、不採択に終わる計画書を「審査官の心を動かす物語」へ、そして不毛な庁内調整を「仲間を巻き込む翻訳術」へと変える、具体的な技術を解説します。
これは精神論ではなく、明日から使える実践ノウハウです。あなたの重たいタスクを、地域を動かす「やりがい」に変えるヒントが、ここにあります。
国の住宅政策を読み解く! 住生活基本計画(全国計画)の基本と最新動向
国が示す住宅政策の基本方針「住生活基本計画」の背景と構成を解説。
計画に基づいた地方自治体の住宅政策への影響や、まちづくりとの関係性を実務目線で整理しています。
集めて効率、でも格差も?コンパクトシティのメリットとリスクを整理
拠点集約型のまちづくり「コンパクトシティ」について、効率性やコスト削減といった利点と、
地域格差の懸念や住民サービスの偏在といった課題を整理し、今後の方向性を検討します。
都市計画はトップダウン、まちづくりはボトムアップ。その違いと関係性を整理
都市計画とまちづくり、それぞれの成り立ちと目的の違いをわかりやすく整理。
行政主導と住民参加のバランスをどう取るか、両者を連動させた地域整備の在り方を考えます。
スーパーシティ構想でまちづくりはどう変わるか
AIやビッグデータを活用した次世代都市「スーパーシティ」の実現に向けた国の構想を解説。
テクノロジーとまちづくりをどう融合させるか、実装に向けた現場の視点で読み解きます。
コンパクトシティで未来を創る!人口減少時代における都市開発の新潮流
人口減少・高齢化が進む中、持続可能な都市のあり方として注目される「コンパクトシティ」。
都市機能を集約し、効率的で暮らしやすい地域づくりを実現するために必要な制度や手法を、多角的な視点からわかりやすく解説しています。用途地域や景観形成、公共交通との連携など、まちづくりに関わるすべての方に役立つ知見が詰まった実務ガイドです。
合意形成の基本と進め方:まちづくりにおける対話の力
まちづくりでは、多様な立場や価値観を持つ人々が協力し、共通の目標に向かって進むための「合意形成」が不可欠です。
このページでは、合意形成の基本的な考え方や進め方、成功のポイントについて、わかりやすく解説しています。
地域の未来を共に築くための対話の力を、ぜひ学んでみてください。
都市計画法
総合設計制度・高度利用地区・特定街区・緩和制度を徹底解説。都市計画制度の使い方まとめ
総合設計制度や高度利用地区、特定街区など、都市の高度活用を可能にする都市計画制度を網羅的に解説。
法的な仕組みと柔軟な緩和制度の活用法を学び、土地利用の可能性を最大限に引き出すヒントが詰まっています。
都市計画ってこんなに面白い!法律の力で理想のまちをデザインする方法
私たちが日々暮らす街は、どのようにして形づくられているのでしょうか。
このページでは、都市計画の基本的な考え方や、法律がどのように街づくりに関わっているのかをわかりやすく解説しています。
都市計画法の概要や、まちづくりにおける法律の役割について知ることで、より良い街を目指すための第一歩を踏み出しましょう。
法令関係
補助金だけじゃない!優良建築物等整備事業のメリット・デメリットと賢い使い方
都市の空間品質向上を図る「優良建築物等整備事業」について、補助金制度の解説にとどまらず、
実務者としてどう活用するか、どのような場面で有効かを具体的に整理しています。
合意形成の基本と進め方:まちづくりにおける対話の力
まちづくりでは、多様な立場や価値観を持つ人々が協力し、共通の目標に向かって進むための「合意形成」が不可欠です。
このページでは、合意形成の基本的な考え方や進め方、成功のポイントについて、わかりやすく解説しています。
地域の未来を共に築くための対話の力を、ぜひ学んでみてください。



